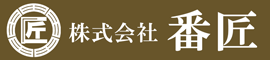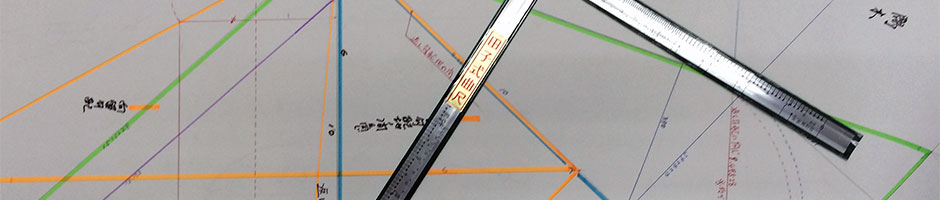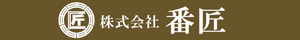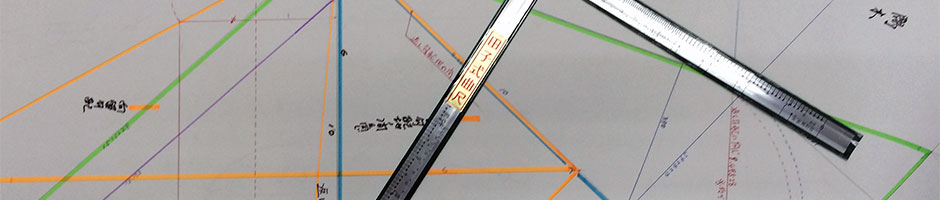
番匠は日本の森林を守ります
日本の建築技術を伝承し、環境を大切にします
未来に伝えたいさしがねの技(第7回)
前回(第6回)では、基本となる棒隅からの勉強ということで、小平起しによる棒隅の論理についてご紹介し、隅木展開図の作図方法について説明しました。今回は束と隅木の取合いを第1図にてご説明し、第2図については投げ墨の求め方を詳しくご説明申し上げます。
≪束と隅木の取り合い(第1図)≫
イ、先ず束2面の①に垂木下端峠を定め、①から②へ平勾配を定めます。
ロ、平勾配に垂木寸法を立成に取り、垂木上端を平行に決めます。②から③に向けて矩を巻きます。
ハ、③から隅木半幅を裏目で戻り、隅木側面が束面と合う位置を隅木胴付きとし、これを三合の基点として、棒隅の場合、半勾配を引き渡します。
ニ、込栓については化粧の場合、小屋組みの場合、また本中栓を打つ場合、他色々有ります。一番栓の効き目のある所に適切に打つのが良いと思われます。

第1図 束と隅木の取り合い
≪投げ墨(第2図)≫
投げ墨については色々な説明がされていますが、私は単純に考え、どのような多角形の場合でも投げ角度を正しく出す方法をご説明したいと存じます。
今回は成りの大きな垂木を仮設し、それと同寸にて隅木の成りを決め、垂木を直角に切ってその角度を隅に移す。つまり、隅木に垂木の直角度がどのように変化した角度になるか、また棒隅の場合、
どのように考えたら良いかを田子流でご説明いたします。これは平勾配の屋根には必ず返し勾配の屋根が、見えないところにあるということです。そう考えたとき、答えが自ずと出てきます。
イ、作図による求め方(どのような角度でも可能)
ロ、隅勾配立水にての求め方
ハ、隅勾配水平による求め方
ニ、返し隅勾配による求め方
ホ、隅木直による直投げの求め方
ヘ、棒隅に限り、尺のさしがねで平勾配を知ってどんな勾配でも表
目と裏目の関係を知り、暗算にて直投げを算出する方法
まだ、幾つか投げ墨の求め方がありますが、これら6種類の求め
方について、第2図で説明しています。

第2図 投げ墨
田子式規矩法大和流六代目 棟梁 田子和則
月刊 住宅ジャーナル 2016年6月号(VOL91)に掲載